南海トラフ地震の発生確率は、2025年1月に発表された最新のデータでは、今後30年以内にマグニチュード8~9級の地震が発生する確率が「80%程度」とされています。
これは今後30年に必ず来るとの事でしょう。もしくは明日くるかもしれません。
実際に大きな災害が起これば防災グッズなど役にたたないかもしれません。
その時に役に立つのは知恵や知識なのかもしれません。
自分が助かる方法も大事ですが緊急時に大事な人を守る助ける事をイメージすれば、
日々いろんな努力
想定外に備える – 防災の新しいパラダイム
近年、世界中で「想定外」という言葉をよく耳にします。大規模な自然災害が発生するたびに、その規模や被害の程度が「想定外」だったと報告されます。しかし、本当に「想定外」なのでしょうか?そして、「想定外」に対して、私たちはどのように備えることができるのでしょうか?
従来の防災パラダイムの限界
これまでの防災対策は、過去の災害データに基づいて、「想定内」の範囲で対策を立てることが一般的でした。しかし、気候変動による異常気象の増加や、都市化による災害リスクの変化など、私たちを取り巻く環境は急速に変化しています。従来の「想定内」の考え方では、もはや十分な備えとは言えないのです。
新しいパラダイムシフトの必要性
これからの防災には、「想定外」を「想定内」に取り込む柔軟な思考が必要です。具体的には以下のような視点の転換が求められます:
1. レジリエンス(回復力)の重視
単なる予防や対策だけでなく、災害後の回復力を高めることが重要です。例えば:
- コミュニティの絆を強化し、互助の体制を整える
- 複数の避難経路や通信手段を確保する
- 生活必需品の備蓄を分散して保管する
2. 創造的な想像力の活用
「ありえない」と思われることも、実は起こりうるという前提で考えます:
- 複数の災害が同時に発生するシナリオ
- ライフラインが長期間停止した場合の対応
- デジタル機器に依存できない状況での対処法
3. 適応型の防災計画
固定的な計画ではなく、状況に応じて柔軟に対応できる体制づくり:
- 定期的な防災計画の見直しと更新
- 様々なシナリオに基づく訓練の実施
- 最新の技術や知見の積極的な導入
個人レベルでできること
新しい防災パラダイムは、行政レベルだけでなく、個人レベルでも実践できます:
- 情報リテラシーの向上
- 災害情報の収集と分析能力を磨く
- SNSでの誤情報に惑わされない判断力を養う
- 多層的な備え
- 非常食や防災グッズの定期的な見直し
- 家族との連絡手段の複数確保
- 地域コミュニティへの積極的な参加
- スキルの習得
- 応急手当や救命講習の受講
- 災害時のメンタルヘルスケアの知識
- 基本的なサバイバルスキルの習得
まとめ
「想定外」に備えるということは、実は「想定外をなくす」ことではありません。むしろ、あらゆる可能性を受け入れ、それに柔軟に対応できる能力を養うことです。新しい防災パラダイムは、私たち一人一人の意識と行動の変革から始まります。
災害は避けられないかもしれませんが、その影響を最小限に抑え、より強靭な社会を作ることは可能です。「想定外」を恐れるのではなく、それを前提とした新しい防災の在り方を、共に考え、実践していきましょう。


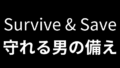
コメント